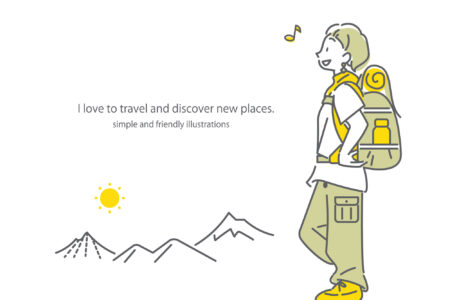7月、ある建設会社の安全衛生協議会総会にて、安全講話の機会をいただきました。今回のテーマは「コミュニケーションエラー」。建設現場に潜む重大事故の背景に、目に見えない“声なきエラー”が潜んでいることを改めて共有させていただきました。
目次
■ 土木と建築で扱いが異なる“命の重さ”
冒頭、私は2年前に発生した二つの重大事故を紹介しました。
一つ目は、2022年7月、静岡での橋桁落下事故。公共工事として発注されたこの現場では、事故後すぐに国土交通省静岡国道事務所が第三者委員会を設置。事故原因の徹底調査が行われ、その結果は公式サイトで公開されています。透明性があり、社会的責任を果たそうとする姿勢が見て取れます。
対して同年9月、東京・八重洲で起きたビル鉄骨崩落事故。こちらも2名の尊い命が失われました。原因は「支保工の強度不足」と元請会社から発表がありましたが、そのミスがなぜ起こったのか?、**どのようなプロセスでチェック機能が働かなかったのか?**といった本質的な部分の検証は不明のままです。
この差は何でしょうか?
一言でいえば、「土木=公共工事」「建築=民間工事」という構造の違いです。公共工事では発注者が責任を持って調査しますが、民間工事では元請主導となり、場合によっては事故の総括が曖昧なまま終わることがあります。
■ 支保工を見て「これは危ない」と思ったけれど…
八重洲の事故では、簡易な支保工が用いられていたとされています。鳶工たちの中には「これで本当に大丈夫なのか…?」と感じた方もいたのではないかと私は推測しています。
しかし、その“違和感”が現場の中で口にされなかった可能性があります。
もしそのとき、「これはおかしい」と声に出せる雰囲気があったなら、事故は防げたかもしれません。
このような“声なき違和感”が現場で黙殺される状態を、私は「コミュニケーションエラー」と呼んでいます。
■ 現場力(レジリエンス)の劣化と、心理的安全性の欠如
「なぜ声が上がらなかったのか?」
それは現場に心理的安全性が無かったからではないでしょうか。
「変なことを言ったら怒られる」
「余計なことを言うと面倒な人だと思われる」
そんな空気があれば、人は黙ってしまいます。
こうした雰囲気が蔓延すれば、「現場力=レジリエンス」は確実に低下します。
レジリエンスとは、変化やトラブルに強く柔軟に対応できる力。
それは「おかしい」を「おかしい」と言える風土があってこそ、育まれるものです。
■ 命の無駄死にを防ぐには
事故で亡くなられた2名の命が、単なる“統計の数字”として処理されてしまうような現場では、同じことが繰り返されます。
間違いを隠すことより、間違いを認め、共有し、次に活かすこと。
その姿勢がない企業には、決して「心理的安全性」は根付きません。
そして心理的安全性のない現場には、真の意味での安全もありません。
■ 最後に 〜「おかしい」と言える勇気を〜
このブログを読んでいるあなたが、もし現場で「ん?」と思うことがあったら、その直感を信じてください。そして、それを声にしてみてください。
もちろん、言いやすい雰囲気を作るのは、管理者の責任でもあります。
私たち大人が「声を上げてもいいんだ」と思える職場を作らない限り、次の若い世代はもっと声を上げにくくなります。
コミュニケーションエラーを防ぐ鍵は、“聴く耳を持つ”ことから始まります。