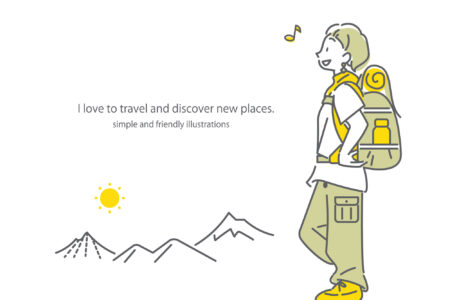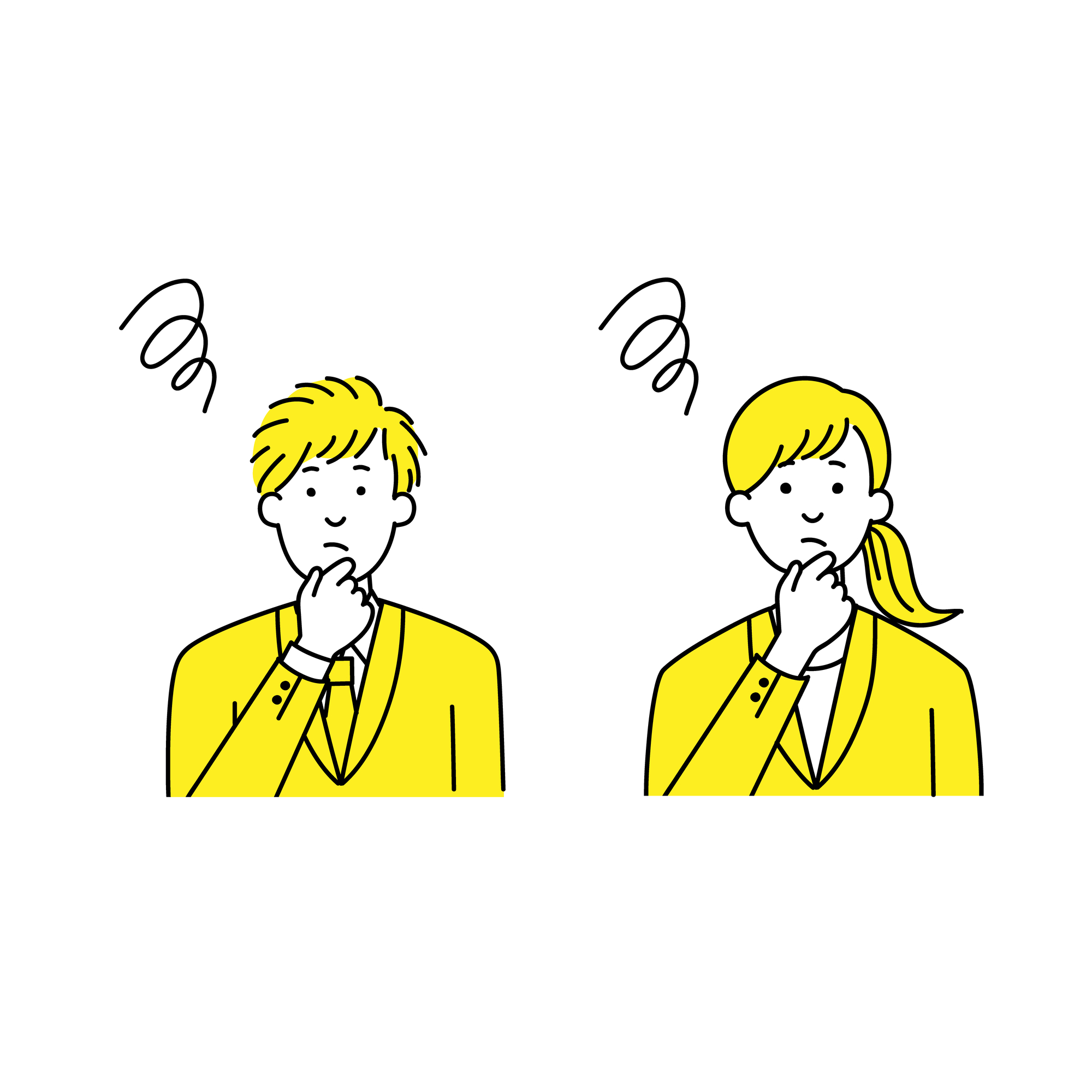
自宅から最寄り駅へ向かう途中、流通センターの大規模工事がようやく完了し、稼働を始めています。物流施設としては立派なもので、周辺環境も整備されたように見えますが、目を凝らすと見逃せない問題が残っています。
◆ 雑草に覆われたままの「完成」公園
この工事に伴い、周辺には2か所の公園が新たに整備されました。
しかし「整備された」と言える状態ではありません。完成引き渡しの時点で、すでに雑草が腰の高さまで伸び、遊具の周囲も土が固められただけ。人が入れるような公園ではなく、「造成途中のまま止まった空地」のような印象です。
◆ 屋根のない東屋
さらに驚かされるのは、東側の公園に設置された東屋(あずまや)。
骨組みは完成しているにもかかわらず、屋根が張られないまま放置されています。柱と梁は立派に組まれているのに、肝心の屋根がなく、日差しも雨も防げない。まさに「東屋の形をしたオブジェ」です。
その周囲には、資材や木材が散乱し、工事の後始末がまったく行われていないことがわかります。施工者の管理意識の低さは明白です。
◆ 施工者だけでなく、神戸市の「受け手責任」
この問題は施工者だけの問題ではありません。
完成した公園は神戸市が引き取る形になっているはずです。
にもかかわらず、現場を確認しないまま「完成」として受け取っている。つまり、行政のチェック機能が働いていないのです。
行政が「発注」や「受け入れ」だけで満足してしまえば、現場はどんなにずさんでも「完了」とされてしまう。これが現場の実態です。
◆ なぜこうした工事が放置されるのか
背景には「付帯工事」としての扱いがあります。
大規模な物流センターなどの都市開発では、周辺環境整備として公園や歩道が“おまけのように”設けられることがあります。
本体工事に比べて優先度が低く、監督も形だけ、最終確認も書類上で済まされる。結果、今回のような「屋根のない東屋」「雑草だらけの公園」が“完成”として引き渡されるのです。
◆ 公共工事に求められる「最後のひと手間」
公共空間の整備は、市民のための事業であるはずです。
しかし、実際には“完成写真”を撮って終わり、という例が後を絶ちません。
屋根のない東屋は、単なる施工ミスではなく、施工管理・行政監督・発注側の三者すべてが「最後の確認を怠った」象徴です。
こうしたずさんな事例が放置されると、地域の信頼も工事への理解も失われていきます。
本来、公園は人が集い、憩うための場所であるはずです。
市民が安心して利用できる空間をつくるためにも、発注者・施工者・行政の「三者責任」をもう一度問い直す必要があります。