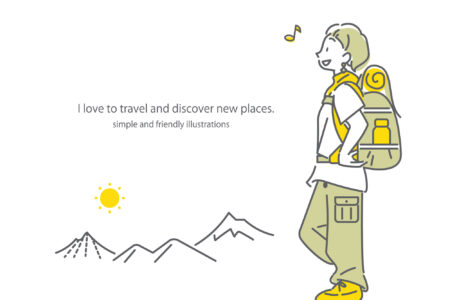秋の深まりとともに、朝晩の冷え込みが増してきました。
紅葉が終わり、木々が静かに冬の装いへと変わっていくころ、暦の上では「霜月(しもつき)」を迎えます。
「霜月」とは、文字どおり“霜が降りる月”という意味。
旧暦の11月、今の暦でいえばおよそ12月上旬から1月上旬にあたり、
霜が降り始めるころにぴったりの名前です。
農作業が一段落し、収穫を終えて冬支度を整える――
そんな日本の暮らしの節目が「霜月」でした。
古来、人々は自然の変化に寄り添いながら月の名をつけており、
霜月はまさに“冬の入り口を告げる月”だったのです。
🏮霜月に行われた行事
旧暦11月(霜月)は、「実りに感謝し、来年の豊穣を願う」行事が多く行われてきました。
- 新嘗祭(にいなめさい):その年の収穫に感謝する最も重要な祭事。
天皇が新穀を神々に供え、自らもいただく儀式として古代から続いています。 - 霜月祭り(しもつきまつり):長野県や静岡県などに今も伝わる神楽行事。
湯を沸かして神々を招き、五穀豊穣や無病息災を祈る“湯立神楽”の形で行われます。 - 冬籠りの支度:火鉢やこたつの用意、薪の準備など、冬を迎えるための生活の知恵。
自然とともに暮らす日本人にとって、これも大切な“行事”の一つでした。
🍵霜月に込められた心
霜月は、
「自然の恵みに感謝し、冬を穏やかに過ごす準備をする月」
とされてきました。
農耕を中心とした時代、人々は実りの喜びを神に感謝し、
次の春に向けて“心と体を休める”時期としてこの月を過ごしていたのです。
現代においても、11月は「文化の日」や「勤労感謝の日」があり、
働く人々や社会の営みに感謝する月でもあります。
つまり、昔の霜月が“自然の恵みに感謝する月”だったように、
今の11月もまた“人の働きに感謝する月”。
時代が変わっても、共通して流れているのは――
「感謝」と「準備」というキーワード。
自然に感謝し、人に感謝し、そして来る冬に備える。
その繰り返しが、私たちの暮らしを支え、心を整えてきたのだと思います。
🌙おわりに ― 霜月の静けさに学ぶ
霜が降りる朝、空気は澄み、音のない世界が広がります。
その静けさは、ただの寒さではなく、“心を整える時間”でもあります。
自然が休息に入るように、私たちも立ち止まり、
一年の感謝を胸に、穏やかに冬を迎える準備をしたいものです。
霜月――それは、自然と人の働きに「ありがとう」を伝える月。