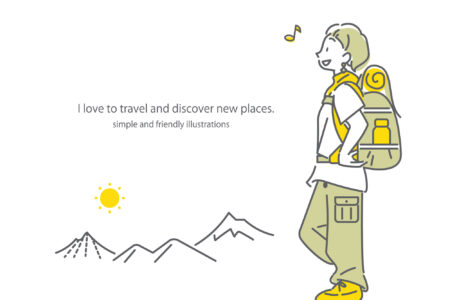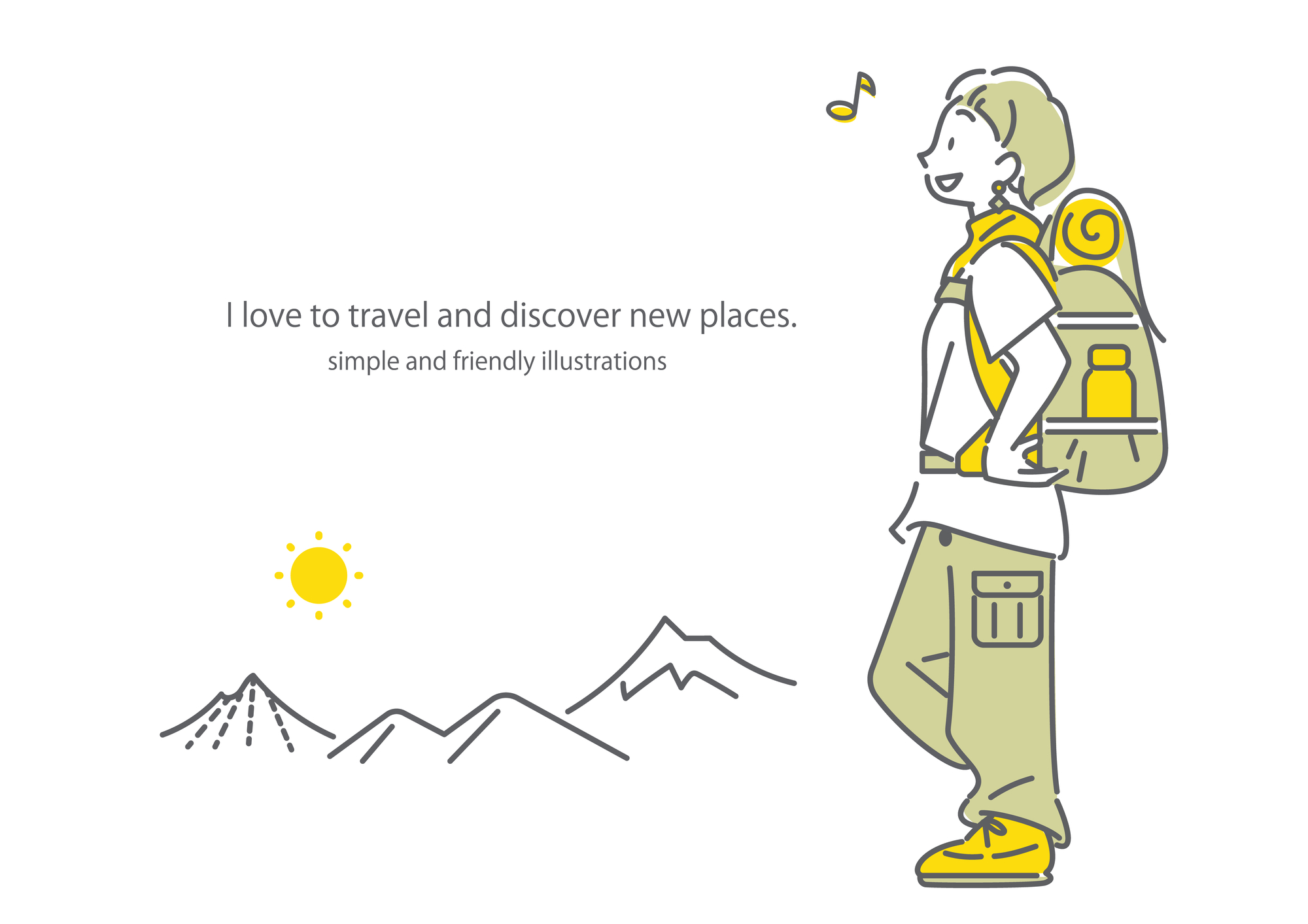
大阪大学大学院への進学を決めてから、私の生活は一変しました。
社会人としての肩書きを離れ、再び学生としての時間が始まったのです。
仕事がない日は、ほとんど毎日学校へ通いました。
火曜日と金曜日はゼミ。
木曜日以外の曜日には、すべて講義を入れました。
学部生向けの講座も、担当教授から「一から基礎を学び直しなさい」と言われ、
20代の学生たちに混ざって受講しました。
最初は戸惑いもありましたが、
一緒にワークショップを行い、実験をし、レポートをまとめるうちに、
年齢の壁は自然となくなっていきました。
同じ班で協力しながら課題に取り組み、
学ぶ喜びを分かち合う仲間ができたのです。
☕ゼミ室が「憩いの場」に
社会人としての経験を持つ私に、学生たちはよく質問をしてきました。
「安全の仕事ってどんなことをするんですか?」
「現場で人の心はどう動くんですか?」
そんな会話をきっかけに、私はゼミ室の整理を引き受け、
みんなが集まって話せる“憩いの場”をつくりました。
昼休みや授業後には学生たちが自然に集まり、
研究や人生、将来のことを語り合う時間が生まれました。
そこには、年齢も立場も超えた“学び合い”がありました。
🧠心理学の基礎を身につける日々
大学院では、応用認知心理学を中心に学びながら、
社会心理学、基礎心理学、統計、実験法なども幅広く履修しました。
講義だけでなく、実験やワークショップを通じて“体験としての心理学”を学ぶことができたのは、
大きな財産になりました。
自分の行動や判断の裏に、どんな心理的プロセスがあるのか。
人はなぜミスをするのか。
安全の現場で抱いていた疑問の多くが、少しずつ“理論の言葉”として形になっていきました。
🌾おわりに ― 学びは、過去と未来をつなぐ
社会人として学び直すというのは、簡単な道ではありません。
けれど、学びの中で出会った若い学生たちや教授との交流が、
私に「人はいつからでも成長できる」という確信を与えてくれました。
心理学の基礎を学びながら、私はようやく気づいたのです。
安全の本質とは、設備やルールの問題だけでなく、
人の認知・判断・行動の仕組みそのものを理解することにある――と。
学ぶことは、過去の経験に光を当て、
未来へ続く新しい道を照らすこと。
大学院での学びは、まさに私にとって“安全の哲学”の出発点となりました。