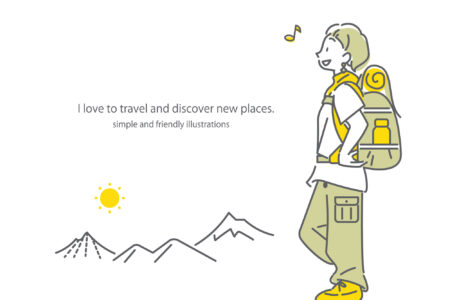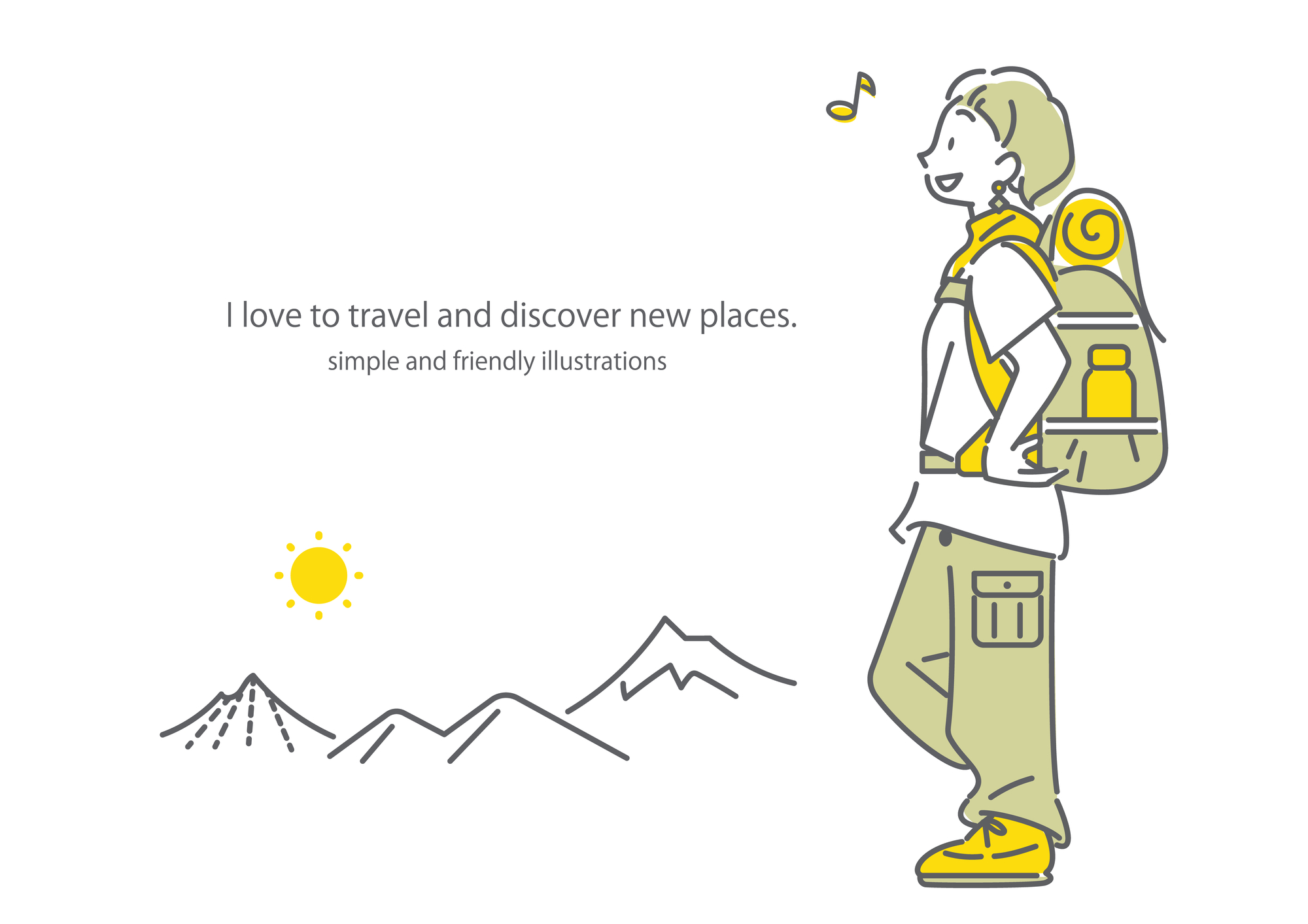
大阪大学大学院に進学すると、大学院生には大学院生室が与えられ、
さらに一台ずつパソコンも支給されました。
授業がない時間は、自分の研究に集中できる――まさに“研究者としての時間”です。
私の研究テーマは、
「指差呼称(しさこしょう)がなぜ現場に定着しないのか」
という問いから始まりました。
現場では「指差呼称をしなさい」と言っても、
時間が経つと形だけになったり、やめてしまったりする。
この“続かない理由”を心理学の視点から明らかにしたいと思ったのです。
そして、もうひとつのテーマとして、
「褒める・叱るという行動が定着にどう影響するのか」
を実験を通じて検証することにしました。
単に“言われたからやる”ではなく、
人の心の動機づけが安全行動の継続にどう関わるのか――
これを解き明かすのが目標でした。
📚論文と専門書に囲まれた日々
研究を進めるためには、まず先行研究を徹底的に調べることが求められます。
そのため、大学院生活の初期は毎日が“読む日々”でした。
院生室には助教の先生が所有する専門書がずらりと並び、
ゼミ生室にも研究室の共有本棚があり、まさに「読み放題」の環境。
授業の合間や通学時間もすべて、論文か本を読む時間に変わりました。
もともと本が好きだった私は、
安全心理学、応用認知心理学、行動科学、モチベーション理論など、
あらゆる分野の専門書を手に取りました。
そして、理解できない部分があれば、先生方に質問に行き、
ひとつずつ確かめながら学びを深めていきました。
🔬現場の疑問を、学問で確かめる
現場で感じた“なぜ”を、
心理学の理論と実験を通じて検証する――。
それは、まるで霧の中に一本の道を探すような作業でした。
現場で「わかっているはずなのにできない」
「大事だと知っていても続かない」
その“人間らしさ”の中に、
安全文化の根っこがあるのではないかと感じていました。
だから私は、
「安全行動の心理」を、現場の目線と研究者の視点でつなげたい。
その思いを胸に、毎日の読書と実験の準備を積み重ねていきました。
🌾おわりに ― 学びは、探求の旅になる
大学院での生活は、忙しさの中にも静かな充実がありました。
読むこと、考えること、そして問い続けること。
それらはすべて、私が現場で見つめてきた“安全の本質”につながっていきました。
現場での経験が問いを生み、
学びがその問いに形を与えていく。
こうして、私は「安全を心理で語る」という道を
少しずつ歩み始めていったのです。