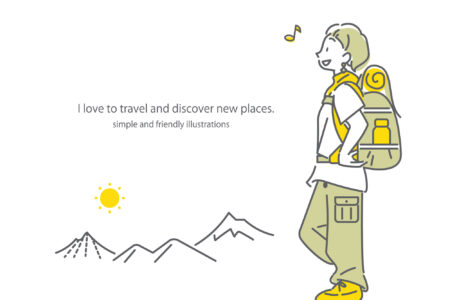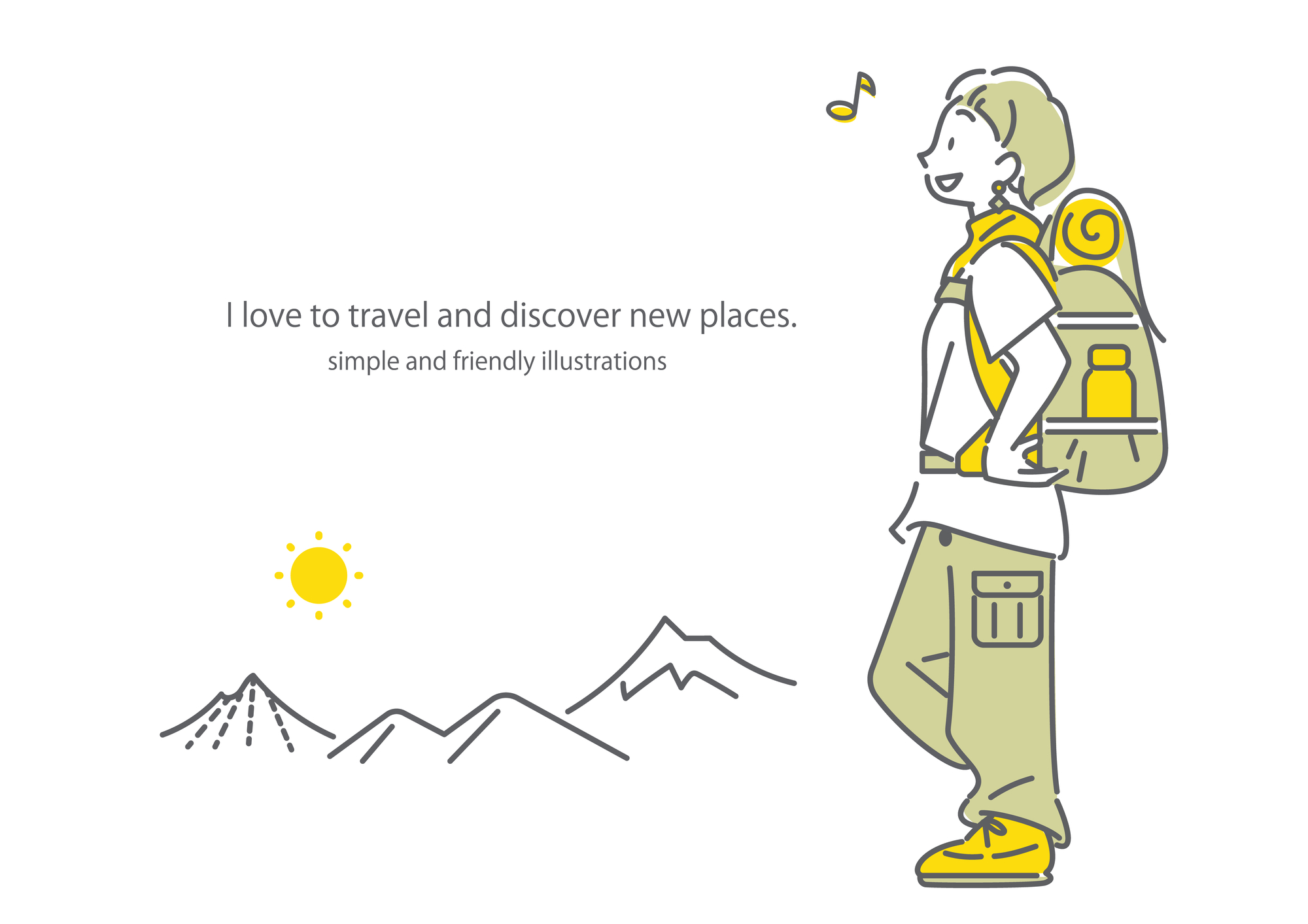
大学院での研究に没頭する日々。
院生室やゼミ室の本棚に並ぶ専門書を読み漁っていたある日、
担当教授から声をかけられました。
「濱口さん、レジリエンス研究会という学部横断の研究会を立ち上げようと思うんですが、
参加してみませんか?」
迷う理由などありませんでした。
私はすぐに「ぜひ参加させてください」と答えました。
🧩学部を越えて、“しなやかさ”を学ぶ
このレジリエンス研究会には、
人間科学科の学生や教員だけでなく、医学部からの参加者もいました。
心理学、医学、看護学、教育学――分野を越えた人々が集まり、
それぞれの立場から「レジリエンス(resilience)」について語り合う会でした。
臨床心理学の学生は「心の回復力」としてのレジリエンスを語り、
医学部の先生方は「身体と精神の適応力」の視点から話す。
そして私は、現場経験を持つ社会人院生として、
「安全の持続性」「現場が困難をどう乗り越えるか」という視点から、
エリック・ホルナゲル教授のレジリエンスエンジニアリングを紹介しました。
立場も専門も異なる人たちが、
ひとつのテーマを多角的に掘り下げる――
この場は、私にとってまさに“学問の交差点”でした。
📖レジリエンスとSafety-IIを学ぶ契機に
この研究会への参加が、私にとって
レジリエンスとSafety-II(セーフティ・ツー)を本格的に学ぶ最初のきっかけになりました。
それまで私は、現場での安全を「事故をなくすこと」「失敗を減らすこと」として捉えていました。
けれど、ホルナゲル教授の理論に出会い、
安全とは「うまくいっていることを維持する力」であり、
組織や人が柔軟に対応し、回復する力そのものなのだと知りました。
この考え方は、私が現場で感じてきた
「完璧な仕組みは存在しない」「人の行動が安全をつくる」という感覚と、
見事に一致していました。
🤝大学院だからこそ得られた対話の場
研究会では、毎回多くの論文を読み、
その内容を参加者同士で討論しました。
心理、医学、教育、それぞれの立場から意見が飛び交い、
自分の考えが磨かれていく。
社会人として現場を知る私の意見も、
他の学生たちにとって新鮮だったようで、
「現場ではそんなふうに考えるんですね」と
よくディスカッションが深まりました。
こうした場に身を置けたこと――
それは、大学院生でなければ得られない貴重な経験でした。
🌾おわりに ― しなやかな安全へ
レジリエンス研究会での学びは、
私に“安全をもっとしなやかに捉える視点”を与えてくれました。
事故をゼロにすることだけを目指すのではなく、
人と組織が変化に対応し、失敗から立ち直る力を育むこと。
それこそが、これからの時代に求められる「安全の本質」だと感じています。
安全とは、壊れないことではなく、立ち直れること。
そして、立ち直る力を育てるのが、教育であり、文化である。